新春企画「象徴の蛇・隠喩の蛇」~2章 世界の蛇信仰を探る~ |
メイン
2013年01月09日
なぜ仏教がインドで根付かなかったのか?4~カーストに繋がる身分制度の形成~
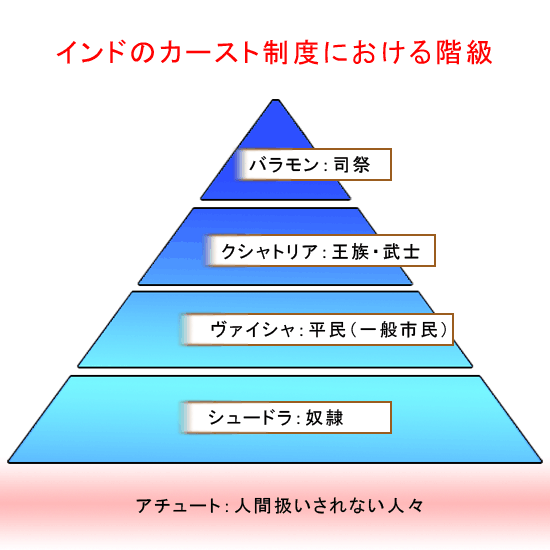
リンクよりお借りしました~
前回の記事では、インドへのアーリヤ人の進入と先住民との融合、そして農耕社会への移行について書きました。
農耕社会を成立させてきたインドでは、生産体制が安定化し、司祭者や王族に余力が出てくるようになります。その中で、自らの立場を守るために、のちのカースト制度に繋がる身分制度:ヴァルナが形成されていきます。
その過程の内容を紹介します。
続きを読む前に、こちらをクリック! 

以下、ヴァルナ制度の内容です。
『古代インドの文明と社会』山崎元一著 より
○四つのヴァルナの形成
農業技術が向上し十分な余剰生産がえられるようになったため、生産に直接たずさわる必要のない司祭階級や王侯・武士階級の形成が促された。かれらは前期ヴエーダ時代の部族司祭とラージャニヤの後継者たちであるが、前代にくらべてはるかに排他的な階級となっている。
そうした階級は「色」を意味する「ヴァルナ」という語で呼ばれている。この時代になると先住民との混血も進み、肌の色と身分・階級との対応関係はほとんどなくなったが、ヴァルナという語はそれ以後も、身分・階級の意味に用いられつづけたのである。
第一のヴァルナの呼称バラモンは、ヴェーダの聖句にそなわる呪術的な力「ブラフマン」をもつ者、つまりヴェーダ聖典を伝持しヴェーダの祭祀を執り行う者を意味している。
第二のヴァルナの呼称クシャトリヤは、クシャトラ(権力)をもつ者という意味である。これら両ヴァルナは支配階層を形成している。
これに対し前代の一般部族民ヴィシュは、上位の両ヴァルナから切り離され、生産と貢納を役割とする第三のヴァルナとなった。このヴァルナの呼称ヴァイシャは、ヴィシュから派生したものである。
アーリヤ人の支配下に置かれた先住民の多くは、隷属的な奉仕階級シュードラとなった。おそらくシュードラに近い発音の名で呼ばれた先住民がアーリヤ人の隷属下に置かれ、この固有名詞がのちに同じ境遇の者が属する階級の呼称となったのであろう。
以上の四ヴァルナから成る社会制度が成立したのは、後期ヴェーダ時代の半ばのことである。
ヴァルナ制度のきっかけとなったのは最上位にいる、司祭者(バラモン)。いかに自分の身分を守るかという意思で身分制度を形成していきます。
●バラモン・ヴァルナの形成
○特権身分の要求
農耕社会の成立とともに、自然の災害から国と住民を守るための祭祀の重要性はいよいよ高まった。司祭者バラモンはこの機会をとらえ、自己の特権的地位を確保しようと努めている。
そのために採用した手段の第一は、祭祀を複雑にしてそれを独占することであった。かれらの説くところによれば、祭祀は絶対的な力をもち、それが規則通りに行われるならば、神々も司祭者の意思に従わざるをえないという。かれらが不注意に、あるいは故意に祭祀の手順を違えるならば、大きな富を費やした祭祀の全体が無効となるだけでなく、災いの原因にもなるのである。
要するにバラモンは、祭祀を通じて神々を動かし、自然界の諸現象を支配できる者たちということになる。こうしたバラモンを司祭者とする祭祀万能主義の宗教は、バラモン教と呼ばれる。
第二の手段は、厳格な婚姻規則を定めて排他的な内婚集団をつくり上げることであった。司祭者の家に生まれた男女の結婚のみを正当とし、その他の組み合わせの結婚を原則的に禁じたのである。司祭者の家に生まれた子は幼いときから特別の専門教育を受け、おもにその知識を自分の子に授ける。こうして司祭職は、バラモン・ヴァルナの内部で世襲されることになった。
第三の手段は、身分秩序の最高位を獲得するために、自分らを「人間と神との仲介者」「人間の姿をした神」「ア-リヤ人の純粋な血を引く最清浄な存在」などと、くり返し主張することである。こうした主張はのちに、バラモン・ヴァルナを最清浄・最高位とし不可触民を最不浄・最下位とするカースト社会の身分秩序の形成を促すことになる。
第四の手段は、自己の生計を確保するための機会を増やすことである。司祭者たちは祭祀や宗教教育に対する報酬で生計を立てねばならず、戦士になることや農業・牧畜・商業という庶民の職業に従事することは原則的にはできない。そこでかれらは、王に向かって祭祀を頻繁に挙行するよう奨励し、また上位三ヴァルナ(アーリヤ)の家長に向かって、日常の宗教儀礼に少なくとも一人のバラモンを招くよう求めた。
バラモンはまた、上位三ヴァルナの子弟にヴェーダの教育を義務づけることにより、宗教的権威と生計の手段をより確実なものにした。上位三ヴァルナの男児は、十歳前後にウパナヤナ(入門式)を挙げてバラモンのもとに弟子入りすることになったのである。
この入門式はアーリヤ社会のメンバーとなるための重要な儀式であり、第二の誕生とみられた。
上位三ヴァルナに属する者は、人生で二回の誕生を経験するためドヴィイジャ(再生族)と呼ばれ、母親の胎内から生まれるだけのシュードラはエーカジャ(一生族)として差別の対象となった。
このようにクシャトリヤもヴァイシャも、ヴェーダ聖典を学び、それぞれの家の小さな祭式を自ら執り行ったのである。しかしバラモン以外の者が他人のために祭式を執り行ったり、他人にヴェーダを教授したりすることは厳しく禁じられた。
このように、バラモンは徹底して自らの優位性を確立しようとしました。
しかし、バラモンは絶対的な身分制度を確立しようとしたのではなく、相互依存を図りながらお互いの身分を守るための制度という位置付けで考えていたようです。
○クシャトリヤとの相互依存
バラモンとクシャトリヤが身分秩序の最高位をめぐって争うこともあった。バラモンがヴェーダ文献のなかでクシャトリヤに勝ることをくり返し強調するのは、そのためである。
しかしそのバラモンも、クシャトリヤと相互に利用しあってはじめて支配階級になりうることは十分にわかっていた。「バラモンとクシャトリヤは相互依存の関係によって共に栄える」というのがヴェーダ文献の説くところである。
インド古代史を通じてバラモンは、宗教や儀礼にかかわる議論では王権に対する自己の優越をあくまでも主張したが、現実の生活においては、王に従属し、与えられた職務を果たすことによって地位と収入を保証されている。王とバラモンのそうした関係をまとめてみるならば、次のようになろう。
バラモンはまず、特別な儀式によって王権の正統性を保証し、また呪術の力によって王と王国に繁栄をもたらす。こうした役割を果たすバラモンのなかで最高位にあるのが、宮廷司祭長のプローヒタである。
次にバラモンは、王の守るべき神聖な義務を説くことによって、政治に参加した。王は法の制定者ではなく、バラモンの伝持する聖なる法(ダルマ)に従って統治する者とみられたからである。この面でもプローヒタが指導的役割を果たしている。
さらに知識階級としてのバラモンは、大臣や裁判官として、また上下の役人として王に奉仕する。かれらが国政の運営と、国家の秩序の維持の上に果たした役割はきわめて大きい。
また、出自で厳密に身分制度を規定しているように見えますが、実体は混血も進んでいたようです。
やはり都合良く、柔軟に制度を利用していたようです。
○混血バラモン
バラモン・ヴァルナは純粋なアーリヤの血を保持する内婚集団ということになっているが、現実にはさまざまな出身の者を受け入れている。
アーリヤ化した先住民のなかからも、ヴェーダ聖典と儀礼を学び、バラモンと称する者が出た。バラモンのパラシュラーマが祭祀に必要な数の司祭者を見つけることができなかったため、火葬の薪から六〇人の男を作りバラモンの地位を与えたという話や、英雄ラーマが多数の山岳民の出身者をバラモンと認めたという話がある。これらは先住民がバラモン・ヴァルナに組み込まれた事実を語るものであろう。
混血者や先住民のバラモン・ヴァルナへの編入が見られたのは、とくにアーリヤ社会の周縁部においてであった。ガンタス・ヤムナー両河地域のバラモンは、周縁部のバラモンを「バラモンと自称するにすぎない者」として蔑視している。しかし、かれらの活動があってはじめて、アーリヤ文化はインド亜大陸全域におよぶことになったのである。
バラモン、クシャトリヤという上位層に対し、ヴァイシャ、シュードラという庶民も身分制度に組み込まれていきますが、過酷な差別があった訳ではなく、例えば奴隷という存在はほとんどいなかったなど、身分差はありながらも、生活は出来ている状態だったようです。
●庶民と下層民
○ヴァイシャの経済活動
アーリヤ部族の上層が、この時代に上位両ヴァルナを形成したのに対し、一般部族民は、農耕・牧畜などの生産活動によってそれら両ヴァルナを支える第三のヴァルナ「ヴァイシャ」とされた。かれらは生産物の一部を王に納めたが、それは自分たちを保護してくれる王に酬いる「分け前」、ないし王の「取り分」と説明されている。こうして組織的な徽税制度の第一歩が踏み出された。
しかしヴァイシャは、シュードラとは異なりアーリヤ社会の正式メンバー「再生族」であり、ウパナヤナ(入門式)を挙げ、バラモン教師のもとでヴューダ聖典を学ぶ資格を与えられていた。
ヴァイシャのなかから、獲得した富を商業活動に振り向ける者も現れた。かれらが住みついたのは王侯の居城のある「都市」や、街道沿いの町であったが、その活動はいまだ小規模にとどまっていた。貨幣や文字の使用もまだ始まっていない。
○厳しいシュードラ差別
ガンジス・ヤムナー両河地域に進出したアーリヤ人に対し、先住民は強く抵抗することはなかったようである。先住民のなかからア-リヤ化した個人や集団も出たが、多くの者は第四のヴァルナ「シュードラ」とされた。また敗戦によって、あるいは従事する職業によって、シュードラの地位に落ちたアーリヤ人もいたことが想像される。シュードラに与えられた義務は上位三ヴァルナへの隷属的奉仕であり、さらに手工芸や芸能の仕事もかれらの役割とされた。
シュードラは隷属民として差別されたが、奴隷とは異なり、一般に自分の家族をもち、わずかではあるが財産を所有している。当時の社会には主人の所有物として売買や譲渡の対象となる「奴隷」も存在していたが、奴隷制は古代のインドでは発達しなかった。これはシュードラという隷属階級が存在したからであろう。高価かつ喪失(病気・死)の危険の大きな奴隷を手に入れるよりは、シュードラを使用するほうが有利なのである。
女性の地位は前代にくらべて低下したようである。女性は宗教的にはシュードラに等しいとされ、ヴエーダ聖典の学習はできなかった。しかし妻は夫を助けて家庭の祭式を執り行う役目をもたされており、シュードラの宗数的無資格との違いは大きかった。
○不可触民の出現
後期ヴューダ時代の終わり近くになって、社会の最下層に重要な動きが生じた。浄・不浄の観念が発達し、排泄、血、死などに関係する行為や物が極度に不浄視されるようになった結果、それらにかかわる職業に従事していた人びとが、不可触民の地位に落とされたのである。
不可触民の起源について、これまでさまざまに論じられてきたが、なお未解明の部分が多い。ただし確実にいえることは、バラモンが自己を最も清浄な存在と主張しつつ身分秩序の最上位を確保したこの時代に、不浄とされる賎民集団が社会の最下層に押し出されるようにして形成されたことである。
賎民視されるにいたった諸集団の多くは、ア-リヤ社会の周縁部に住む狩猟採集民であった。狩猟採集民のなかには、農耕民となってア-リヤ社会に編入される者も出たが、そうした機会を失った者たちは、旧来の習俗を維持しつつ、アーリヤ社会の最下層に組み込まれた。
また、これら賎民視された諸集団の間にも上下の区別がもち込まれ、その最下位にチャンダーラと呼ばれる不可触民が置かれた。チャンダーラという呼称は、アーリヤ人に征服された先住民部族の名から出たものらしい。
不可触民は、はじめシュードラの最下層に位置づけられていたが、やがてシュードラ以下の存在、第五のヴァルナとみなされるにいたった。
チャンダーラには清掃、体刑執行、屍体処理などの仕事が割り当てられている。
不可触民の存在は、ヴァイシャとシュードラにある種の優越感をもたせ、経済活動の担い手であるかれらと支配階級との間に生ずる緊張関係を緩める効果をもっていた。これ以後、不可触民制は、ヴァルナ・カースト社会の安定的な維持に不可欠な装置として発達することになる。
○ヴァルナ制度のひろがり
ガンジス・ヤムナー両河地域で成立したヴァルナ制度は、アーリヤ文化の伝播にともなって周辺地域に伝わり、やがてインド亜大陸全域におよぶことになる。こうした伝播には、必ずしもアーリヤ人の大量移住を必要とはしない。南インドのドラヴィダ世界に見られたように、先住民の有力者が北の文化と制度を受け入れて、王権の強化と社会の秩序化を図るということもあったからである。
先住民のこうしたアーリヤ化にさいして、バラモンの果たした役割は大きかった。かれらは祭式の報酬と布施に頼って生活する者であり、したがって保護者を求めてしばしば遠隔の地に移住することも辞さなかった。周縁の地に赴いたバラモンのなかには、先住民の有力者の保護を受けつつアーリヤ化の先駆となる者も出たのである。
ヴァルナ制度の理論は、最高のヒンドゥー法典とされる『マヌ法典』において完成する。またこの制度は、六、七世紀ころから複雑に発達するカースト制度の基本的な枠組みとしても機能することになる。そして時代や地域によって厳しい緩いの差はあるものの、カースト社会の大きな枠組みとして、日常の生活で意識されるか否かにかかわらず、今日まで存続しつづけている。
近年の例でいえば、庶民の日常生活においては、バラモンの場合を除きヴァルナの区別がとくに意識されることはない。しかし特定のカーストが社会的ランクを上昇させようと試みるとき、かれらは突然バラモンやクシャトリヤといった高位ヴァルナの子孫であることを主張しはじめるのである。
このように、ヴァルナという身分制度がインド全土で見事に確立していきますが、なぜ、現代のカースト制度にまで繋がるこの身分制度が、存続し続けているのでしょうか?
それは、インド人に脈々と受け継がれている、輪廻思想が影響しています。
○業・輪廻思想の誕生
業・輪廻思想はインド人の死生観の根本である。また仏教にともなってわが国に伝来し、日本人の死生観に大きな影響を与えた。寺の僧侶の説法に六道輪廻という語が出てくるが、これは霊魂がこの世の善悪の行為(業)に従って地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上という六種の世界の間で生死をくり返すことを意味している。われわれはだれでも「地獄に堕ちるぞ、畜生に生まれるぞ」とおどされた経験をもっている。
インドの気候は雨季と乾季がはっきり分かれており、乾季の間に干上がった大地は雨季の到来とともに蘇る。そしてあたり一面緑の世界となり、地中では虫どもが活動を始める。輪廻思想の起源を先住民に求める説も有力であるが、いずれにせよこうした雨季・乾季の循環が見られるインドの大地でこの思想は誕生した。
>
そのさい、どのような姿をとって再生するかは、前世の行為(業)によってきまる。祭祀や布施や善行に努めた者はパラモンやクシャトリヤとして生まれ、悪を行った者はシュードラや畜類などとして生まれる。さらに極悪の者は祖先たちの道に入ることもなく、単に虫けらとして地上で生死をくり返すのであるという。
>
この世の生まれは前世の業の結果であるから、シュードラに生まれようと、不可触民に生まれようと、宿命として甘受せねばならないのである。こうした宿命観は、ヴァルナ制度や、のちのカースト制度を思想的に支えることになる。 俗世を支配する王といえども、輪廻転生から自由ではありえない。古代インドの王たちは、善政や大供犠・大布施・寺院建立といった功徳を積んで来世に天国に生まれることを願い、悪政や不信心の報いで地獄に堕ちることを恐れた。
この輪廻思想により、信仰心が高いインド人は、神官(バラモン)を頂点とする身分制度を甘んじて受け入れました。また、元々の共同体も残存し、職業の役割分担も含めて、安定的な秩序を守るための、社会統合、共存のシステムとして確立していったと言えます。
このように古代に身分制度が確立し、古代国家が成立していきますが、その後、私権拡大とともに権力闘争も激しくなります。
この続きは次回、お楽しみに~ 😀
投稿者 vaio : 2013年01月09日
TweetList

トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://web.joumon.jp.net/blog/2013/01/1471.html/trackback
