2007年12月11日
2007年12月11日
森の民にとっての精霊
漁撈・採取を生業としてきた縄文人ですが、彼らの活力源でもあった「精霊」とは、どのようなものだったのでしょう?
今回は、ボルネオの先住民を通じて、縄文人の精霊観に迫ってみたいと思います。
森をめぐる直観【参照】
同じボルネオ島の先住民でありながら、焼畑稲作民カリスと狩猟採集民プナンの森に対する態度は、ずいぶんとちがう。
カリス人は、夜と森をひどく畏れている。夜と森には、精霊が跋扈するからである。精霊は、人を、人の魂を魅惑したり、誘拐したり、攻撃することを方向づけられた存在として知られている。魂が精霊との関係の諸相に入ると、人は病気になったり、死んだりするとされる。夜、一人で歩くことができるのは、精霊と戦うことができる「バリアン」と呼ばれるシャーマンくらいのものだと、カリスはよくいう。森のなかを歩いて隣村にいくときには、カリスは、数人で連れ立って歩いてゆくことが多い。森のなかで会った人が無言であることを心配する。無言の人物は、精霊の仮姿であり、出会った人(たち)は、近い将来、厄災をこうむるはずだ。森のなかでは、精霊が跋扈しているので、食べ物を食べないし、食べ物に関わる語彙は、別の言葉に置き換えなければならないとされる。食べ物や飲み物に対する決まった作法を怠ると、魂が精霊に捕らえられて、病気や死に至ると考えられているからである。
そのように、カリスの人びとに深く浸透する精霊感覚。その延長線上に、彼らは、人間と自然の関係を、人間と精霊・神の関係へと置き換えて捉えているように思われる。彼らは、自然からの純粋な恵贈(米、森林産物、獲物・・・)を、神や精霊からの贈り物へと置き換えて、観念しようとする。それは、例えば、開墾、火入れ、収穫などの焼畑の作業を開始する前に必ず催される、精霊を呼び出して食べ物と飲み物を捧げる見返りに収穫をもたらすように祈願する儀礼において、顕著に見られる。祖霊や地縛霊などの精霊こそが、収穫と安寧をもたらす存在として観念されるのである。
マオリ人は、「ハウ」という概念を持つことで知られる。それは、「人にだけ憑くのではなく、動物、土地、森、そして村の家にさえ、憑いている。だから森のハウ、生命力、ないし生産性は、それ独特の祭式によって、きわめて慎重に保護されなければならない」とされる。
それは、マオリ人が生み出した、自然の恵みの根本原理とでもいうべきものである。モースが、『贈与論』のなかで、マオリ人にとって、贈り物には、贈り手の「ハウ」が憑いていて、つねに、その贈り手に帰りたがると説明していることはよく知られている。ところが、「ハウ」の本来の意味とは、「ハウ」が、マオリ人がつくり出した「概念」であり、そのような概念としての「ハウ」が、人間に与えてくれる贈与というものを想定して、人間が、儀礼などを行って、返礼をするということなのである。
自然からの純粋贈与、自然との交渉を「ハウ」という概念を用いて捉えようとするマオリ人のやり方に照らせば、カリス人は、自然からの純粋贈与、自然との交渉を、人間と精霊との交渉へと置き換えた上で、それを操作しようとしているのだと見ることができるのではないだろうか。そこでは、精霊や神こそが、特大の価値を与えられることになる。
他方で、プナン社会には、上のカリス社会とは、たいへん異なる森への態度が観察される。プナン人は、森を、精霊が跋扈する場として、畏れの対象として知覚するということは、ほとんどない。彼らは、今日に至るまで、狩猟や採集など、森に重度に依存しており、森は恐怖の対象ではなく、むしろ、熱帯の灼熱から離れて、生きるための糧と清涼を提供してくれる、生の場として意識されている。
さらに、プナン人は、カリス人のように、人間と自然の関係を、人間と精霊・神との関係を通して理解しようとするようなことはない。精霊や神こそが、人間に恵を与えてくれるというふうには、考えない。かといって、マオリ社会のような、自然の恵の根本原理のようなものを幻想して、それに対して、返礼を行ったり、あるいは、感謝の気持ちを表わしたりするようなこともない。わたしは、プナン人たちが、いったい自然からの恵に対して、どのような意識をもっているのかについて、いろいろと調べてきたが、プナンには、自然の恵に対する明白な意識がないということが、彼らの自然観の大きな特長であるというようなことしか、これまでのところ分からない。森に対して、自然に対して、動物に対して、感謝や祈りを唱えるということは、わたしが知る限り、プナン社会では行われていない。
カリスの人々の精霊は、観念操作のたまものであり、言葉は悪いが、「霊感商法」につながるような感覚があります。
一方の、プナン人の精霊=自然観は、極めて朴訥です。
彼らは、どのように、感謝や祈りを表すのでしょう?
知りたいと思った方は、応援よろしくお願いします 🙄
投稿者 naoto : 2007年12月11日
Tweet

2007年12月11日
人類にとって戦いとは
戦争の起源がホットなテーマになっていますね。私もちょいと読んだ本を紹介します。
人類にとって戦いとは
1.戦いの進化と国家の生成
編者 福井勝義・春成秀爾 出版:東洋書林
この本が興味深いのは、国立歴史民族博物館が監修して、学際的な探求の成果を本にした点です。つまり、執筆者は、霊長類学、形質人類学、考古学、歴史学、文化人類学の領域にまたがっているのです。二人の編者は前書きで、「これほど学際的な視点から『人類にとって戦いとは』にアプローチした試みは、日本は無論、世界的にも私は知らない。」と自負しています。確かに、観念の世界の探求としてでなく、様々な視点からの事実を持ち寄り、そこから真実を探求しようとする試みは、可能性を感じるものでもあります。
で、結局何が書いてあるのってことですが・・・、皆さんもいろいろと論じているように、戦争が人類の本性のようなものなのか?それとも人類の歴史の中では、農耕などが発達してきたごく最近のできごとなのかという素朴な問題意識を学際的に探求しようというものです。
私としては、「戦争の起源」という議論が、いまだに答えの見つからない難しい問題なんだということ自体が、新鮮でもあります。確かに、自分でもそんなことを本気で考えたことはなかったですね。
まず、読むに当たって、この本では戦争の定義を「異なる政治統合を持つ集団間における組織的武力衝突」といったんは捉えていますが、それを考古学が対称にする遺跡など「もの」から検証していくのはきわめて困難であるとも言っている。様々な分野の事実と知見を集めてどこまで解明できるのでしょうか?
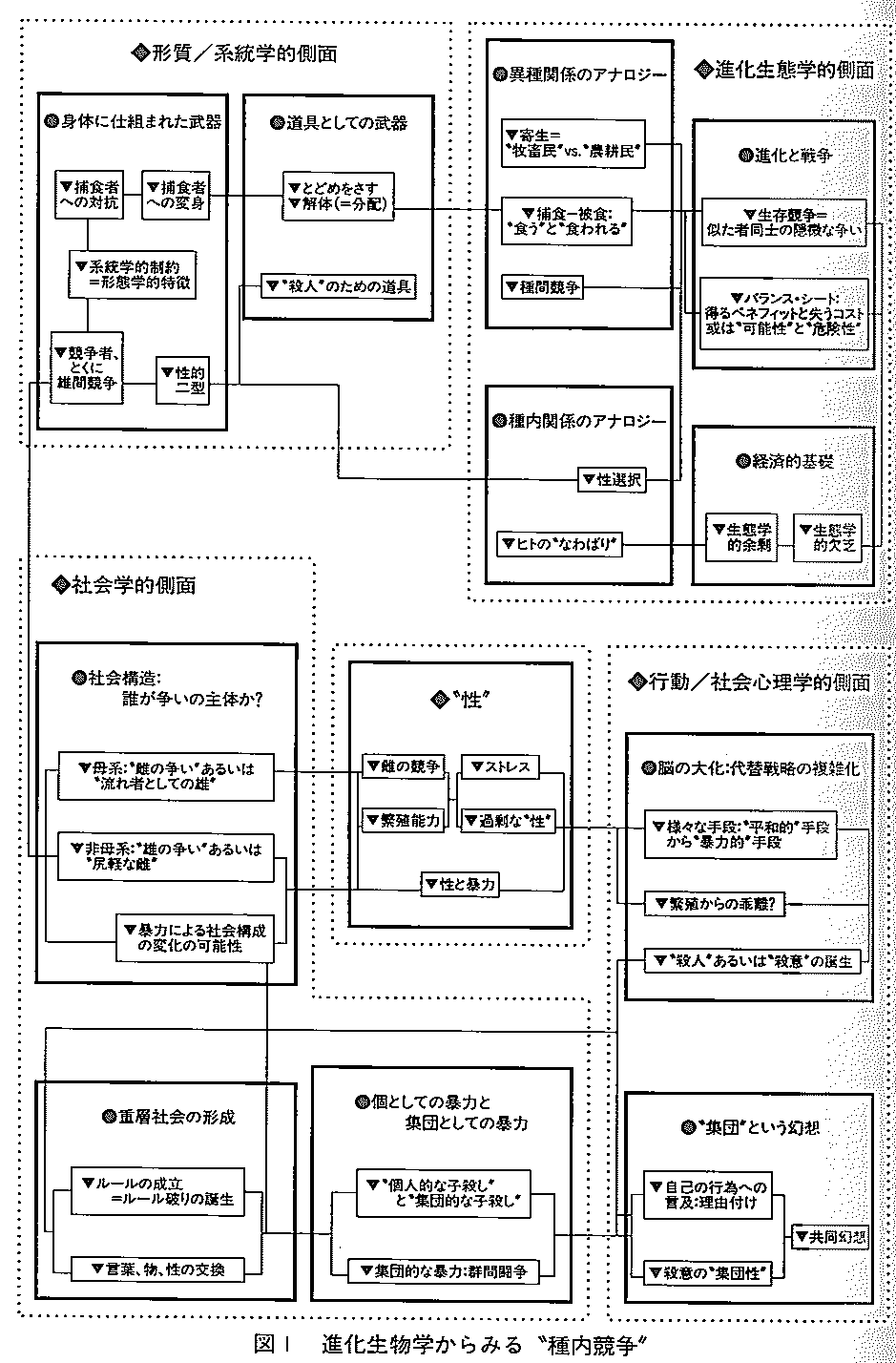
続きを読む
投稿者 hiroshi : 2007年12月11日
Tweet

